長野城跡 長野氏の出自については明らかではありません。南北朝時代には、すでに津市美里地区(旧美里村)の長野の地を本拠とし、一族を旧安濃郡(現在の津市芸濃地区の南半・安濃地区・美里地区・旧津市の大半)の各所に配置し、旧奄芸郡(芸濃地区北部・鈴鹿市南部・河芸地区・旧津市北部)にも勢力を伸ばしていました。 長野氏の出自については明らかではありません。南北朝時代には、すでに津市美里地区(旧美里村)の長野の地を本拠とし、一族を旧安濃郡(現在の津市芸濃地区の南半・安濃地区・美里地区・旧津市の大半)の各所に配置し、旧奄芸郡(芸濃地区北部・鈴鹿市南部・河芸地区・旧津市北部)にも勢力を伸ばしていました。南北朝時代(14世紀後半)には、足利尊氏方有力な武士として、「梅松論」や「太平記」に活躍する様子が記されています。 室町時代の伊勢国は、雲出川を境にして南は伊勢国司北畠氏の支配下にあり、北はあまり強い勢力ではないが、伊勢守護の支配下にありました。室町幕府は北畠氏対策と守護勢力のけん制をはかり、将軍の権力を浸透させるために、当時、国人とも呼ばれた北勢各地の有力武士を直接の家来にすることが必要でありました。この親衛隊の役割を果たした者は奉公衆と呼ばれ、全国で300人以上いました。 有力な国人であった長野氏も奉公衆に属しながら北勢各地の荘園にも勢力をのばし、応仁・文明の乱(15世紀後半)の頃には三重郡、16世紀には桑名にまで進出したこともありました。 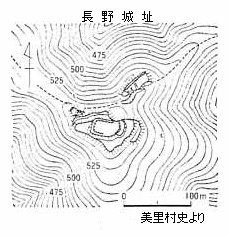 長野城は、美里地区桂畑西方の非常に眺めのよい山頂(標高540m)にあります。城跡からは伊勢湾はもとより、中勢南部の山々や平野が一望できます。地元では“しろんだい・城の台”と呼び、20m×40mの一段高い台状地を中心として、そのまわりを狭い平坦地が階段状にとりまいています。この頃の城にはほとんど石垣は使用されていません。 長野城は、美里地区桂畑西方の非常に眺めのよい山頂(標高540m)にあります。城跡からは伊勢湾はもとより、中勢南部の山々や平野が一望できます。地元では“しろんだい・城の台”と呼び、20m×40mの一段高い台状地を中心として、そのまわりを狭い平坦地が階段状にとりまいています。この頃の城にはほとんど石垣は使用されていません。城跡から尾根づたい北西約300m離れた所には“馬場”とも呼ばれる平坦地があり、その一角には湧水も出ています。城跡の周囲はどこも急斜面が麓まで続き、天然の要害になっています。 この城が文献記録に始めて登場するのは、南北朝時代の争乱を伝える「太平記」延文5年(1360)の記事です。畠山国清らとの抗争に敗れ、京都を脱出した伊勢守護仁木義長は、この長野城で幕府追討軍の六角氏頼・土岐頼康らに対し、2年以上も籠城戦を続けました。「太平記」には、「要害堅固なため、寄手がなかなか近寄れなかった。」と記しています。   |