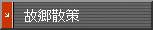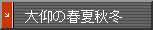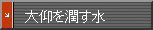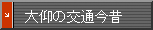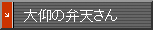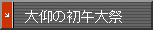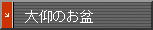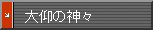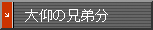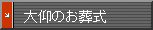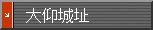筑摩書房「本居宣長全集」は、第1巻から第20巻と別巻3巻から構成されていました。
本居宣長は生涯にわたりおびただしいほどの日記と記録を残しており、それらは第16巻に収録されて
いました。
日記は13冊残されており、往時の生活模様を垣間見る貴重な資料です。
また日記には「委細如二別記一」と注書がされ、慶事や法事の詳細な記録が別記としてまとめられてい
ます。
13冊からなる日記の内訳を次に示します。
・日記(宝暦二年迄之記)
享保15年(1730)5月7日誕生から宝暦二年(1752)2月4日まで
・日記(今井田日記)
山田の今井田家の養子になった寬延元年(1748)11月14日から同三年12月同家離縁に
なるまで
・在京日記 3冊からなる
宝暦二年(1752)3月5日の上京から、同七年10月6日松阪帰郷まで
・目録
宝暦七年(1757)10月6日松阪へ帰ってから以後、同十二年2月28日まで
年中行事などが書かれている。
・日記 7冊からなる
33歳の宝暦十二年(1762)正月1日から、72歳の享和元年(1801)9月29日没す
る直前の9月14日迄
編者の解説によると、宣長は28歳で松阪に戻り医者を開業するとともに国学の道に専念する。ここに
思いを新たにし、10月6日から目録と題する日記の執筆を始めた。
目録は、青春時代自分の感性の赴くまま和文調で書かれた「在京日記」とは異なり、経済的に自立する
生活者として自覚されたとき、繁忙な生活に追われる日常の自己及び周辺の同姓を簡略に記録すること
が最もふさわしいと思われる漢文記録に変わっています。
この貴重な日常の記録から「一丁切り」の言葉を発見することが出来ます。
・宝暦9年己卯5月5日雨天
15日、栄保大姉27回忌、13日、牡丹餅、当町近隣配、14日、非時、同夕一挺切念仏修
行・・・・・
・宝暦9年庚辰4月8日晴天
27日、非時、妙楽時和尚、法樹院、孫左衛門、於林殿、於金殿他、其外手代出入者不レ呼、同夕一
挺切執行、母人諷誦、・・・・・
・宝暦13年癸末2月27日晴天
○明日道喜居士13回忌、因レ之今夕修二一挺切念仏一
・宝暦13年癸末10月6日晴天
○今日非時、法樹院、道有公、與三兵衛、於金殿、於登波殿、茂八等他、今夕一挺切修行之
・明和3年丙戊3月23日晴天
○今年道樹大徳27回忌、今月取越勤、今日非時、今夕一挺切勤
・明和4年丁亥2月27日曇、後雨天
○道喜居士17回忌、今日非時、今夕一挺切相勤
・明和5年戊了10月30日微雨
○恵勝法尼一周忌取越勧業、28日小豆餅配、今日非時、今夕一挺切修行
・明和6年己丑9月29日
今日三回忌日時、夜一挺切修行・・・・・
・明和9年壬辰2月23日
今朝樹敬寺方丈斎供養、非時親類男女等、○夜一挺切修行、委曲如二別記一
○今月晦日、翌朔日江戸大火事
・安永2年癸巳2月24日
・・・・・道喜居士3回忌
・安永2年癸巳10月朔日
丙戌 ○恵勝法尼7回忌取越修行・・・・
・安永6年丁酉2月28日
今日一挺切勤レ之、道喜居士27回忌也、是又同一挺切修行、右兩霊年忌
今度一時勤レ之、委曲如二別記一
・安永7年戊戌3月11日
唱阿大徳50回忌、取越相勤・・・・・
・安永8年己苅3月27日
来正月恵勝法尼13回忌、取越勤、今日赤豆餅配
・天明2年壬寅4月11日
栄保大姉50回忌、今月取越相勤、今日白粥飯配、・・・・・
・天明3年癸卯2月28日
道喜居士33回忌也、・・・・・
・天明4年甲辰4月2日
栄感大姉150回忌引上修行、・・・・・
・天明7年丁未4月8日
行誉慶歩大姉150回忌引上修行、・・・・・
・寬政元年己酉4月24日 (日記なし)
場誉直観道樹大徳50回忌取越
・寬政元年己酉10月朔日 (日記なし)
清誉光雲恵勝法尼23回忌取越
・寬政2年庚戌10月13日
道観居士200回忌也、今日白粥飯配
・寬政5年癸丑10月朔日
辛酉 ○恵勝法尼27回忌、取越相勤、・・・・・
・寬政10年己末10月朔日
丙戌 ○恵勝法尼33回忌、明年正月なり、今日取越勤之・・・・・
・寬政12年庚申2月28日
欣誉道喜居士50回忌也、・・・・・
以上24件の記述が見られます。
安永7年頃から日記に「一挺切念仏修行」の言葉が消えています。
日記の別記として冠婚葬祭の詳細な記録が有り、そのときの出席者、祝いの物、お供え、献立表などが
有り、年忌のところを見ると「法事」の欄が有り、壹挺切、小施餓鬼、諷誦、次念仏と法事の次第と思
われることが記述されています。
日記に記述されてないが、この資料から一挺切念仏が継続されていることが分ります。
■知り得たこと
①一挺切り修行は、亡くなられた日に行われておらず、追善法要時に勤められている。
②日記別記の法事欄にはその次第と思われる内容が記述されており、「壹挺切」記載の下には春庵の
名前があります。
春庵は本居宣長の号であるので、一挺切修行は住職が勤めるものではなく施主が行う法要と推測さ
れます。
本居宣長は生涯にわたりおびただしいほどの日記と記録を残しており、それらは第16巻に収録されて
いました。
日記は13冊残されており、往時の生活模様を垣間見る貴重な資料です。
また日記には「委細如二別記一」と注書がされ、慶事や法事の詳細な記録が別記としてまとめられてい
ます。
13冊からなる日記の内訳を次に示します。
・日記(宝暦二年迄之記)
享保15年(1730)5月7日誕生から宝暦二年(1752)2月4日まで
・日記(今井田日記)
山田の今井田家の養子になった寬延元年(1748)11月14日から同三年12月同家離縁に
なるまで
・在京日記 3冊からなる
宝暦二年(1752)3月5日の上京から、同七年10月6日松阪帰郷まで
・目録
宝暦七年(1757)10月6日松阪へ帰ってから以後、同十二年2月28日まで
年中行事などが書かれている。
・日記 7冊からなる
33歳の宝暦十二年(1762)正月1日から、72歳の享和元年(1801)9月29日没す
る直前の9月14日迄
編者の解説によると、宣長は28歳で松阪に戻り医者を開業するとともに国学の道に専念する。ここに
思いを新たにし、10月6日から目録と題する日記の執筆を始めた。
目録は、青春時代自分の感性の赴くまま和文調で書かれた「在京日記」とは異なり、経済的に自立する
生活者として自覚されたとき、繁忙な生活に追われる日常の自己及び周辺の同姓を簡略に記録すること
が最もふさわしいと思われる漢文記録に変わっています。
この貴重な日常の記録から「一丁切り」の言葉を発見することが出来ます。
・宝暦9年己卯5月5日雨天
15日、栄保大姉27回忌、13日、牡丹餅、当町近隣配、14日、非時、同夕一挺切念仏修
行・・・・・
・宝暦9年庚辰4月8日晴天
27日、非時、妙楽時和尚、法樹院、孫左衛門、於林殿、於金殿他、其外手代出入者不レ呼、同夕一
挺切執行、母人諷誦、・・・・・
・宝暦13年癸末2月27日晴天
○明日道喜居士13回忌、因レ之今夕修二一挺切念仏一
・宝暦13年癸末10月6日晴天
○今日非時、法樹院、道有公、與三兵衛、於金殿、於登波殿、茂八等他、今夕一挺切修行之
・明和3年丙戊3月23日晴天
○今年道樹大徳27回忌、今月取越勤、今日非時、今夕一挺切勤
・明和4年丁亥2月27日曇、後雨天
○道喜居士17回忌、今日非時、今夕一挺切相勤
・明和5年戊了10月30日微雨
○恵勝法尼一周忌取越勧業、28日小豆餅配、今日非時、今夕一挺切修行
・明和6年己丑9月29日
今日三回忌日時、夜一挺切修行・・・・・
・明和9年壬辰2月23日
今朝樹敬寺方丈斎供養、非時親類男女等、○夜一挺切修行、委曲如二別記一
○今月晦日、翌朔日江戸大火事
・安永2年癸巳2月24日
・・・・・道喜居士3回忌
・安永2年癸巳10月朔日
丙戌 ○恵勝法尼7回忌取越修行・・・・
・安永6年丁酉2月28日
今日一挺切勤レ之、道喜居士27回忌也、是又同一挺切修行、右兩霊年忌
今度一時勤レ之、委曲如二別記一
・安永7年戊戌3月11日
唱阿大徳50回忌、取越相勤・・・・・
・安永8年己苅3月27日
来正月恵勝法尼13回忌、取越勤、今日赤豆餅配
・天明2年壬寅4月11日
栄保大姉50回忌、今月取越相勤、今日白粥飯配、・・・・・
・天明3年癸卯2月28日
道喜居士33回忌也、・・・・・
・天明4年甲辰4月2日
栄感大姉150回忌引上修行、・・・・・
・天明7年丁未4月8日
行誉慶歩大姉150回忌引上修行、・・・・・
・寬政元年己酉4月24日 (日記なし)
場誉直観道樹大徳50回忌取越
・寬政元年己酉10月朔日 (日記なし)
清誉光雲恵勝法尼23回忌取越
・寬政2年庚戌10月13日
道観居士200回忌也、今日白粥飯配
・寬政5年癸丑10月朔日
辛酉 ○恵勝法尼27回忌、取越相勤、・・・・・
・寬政10年己末10月朔日
丙戌 ○恵勝法尼33回忌、明年正月なり、今日取越勤之・・・・・
・寬政12年庚申2月28日
欣誉道喜居士50回忌也、・・・・・
以上24件の記述が見られます。
安永7年頃から日記に「一挺切念仏修行」の言葉が消えています。
日記の別記として冠婚葬祭の詳細な記録が有り、そのときの出席者、祝いの物、お供え、献立表などが
有り、年忌のところを見ると「法事」の欄が有り、壹挺切、小施餓鬼、諷誦、次念仏と法事の次第と思
われることが記述されています。
日記に記述されてないが、この資料から一挺切念仏が継続されていることが分ります。
■知り得たこと
①一挺切り修行は、亡くなられた日に行われておらず、追善法要時に勤められている。
②日記別記の法事欄にはその次第と思われる内容が記述されており、「壹挺切」記載の下には春庵の
名前があります。
春庵は本居宣長の号であるので、一挺切修行は住職が勤めるものではなく施主が行う法要と推測さ
れます。