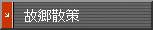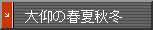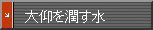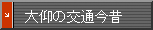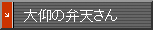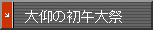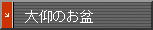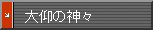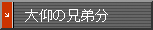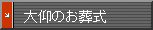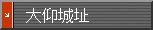それぞれの地域でお盆の行事は行われますが、我が故郷のお盆は8月7日から14日です。
わが故郷も少子高齢化、何かにつけ昔からの仕来たりを守っていくのが困難な時期になってきている
感じがします。
伝統を守るもよし、変えていくのもよし、と言うか仕方ないことなのかもしれません。不思議なこと
に同じ在所の中なのに、組によって少しづつ仕来たりが違うのです。
8月7日(火入れ) |
|---|
| 初盆の家では7日から行事が始まります。 「しょうろうさん」と言ってますが燈篭などを仏壇の周りに飾り付けます。 親戚は8日を目途に初盆見舞いを持ってお参りします。 濃い親戚でビール1ケースが一般的なお供えです。 広出組はどういうわけか、砂糖5Kgをもってお参りする慣わしです。 その年によって時間は変わりますが、上人さんが回向に来てもらいます。家族や濃い親戚で対応しま す。 *平成27年7月の申し合わせで「広出組の初盆見舞いは砂糖5Kgと決まっていたがこれを改め、初盆見舞い志 (お金)」となった。 また、13日の夜のお参りには出席するが、14日の組内の念仏、食事、お寺への精霊さん送りの行事は行わな いことになった。 |
| |
8月13日(棚経) |
|---|
| 10時か11時頃お寺の鐘がゴ〜ンと鳴るを合図に、上人さんが檀家の家を一軒一軒回りお盆のお 勤めが行われます。 上人さんと同行するのが檀家の中から選ばれた寺年番です。 ●寺年番の役割 寺年番は檀家の中から2人選ばれた世話役で、任期は1年間の持ち回りです。 この役は年度末3月でなく、お正月の飾り付けで次の寺年番に引き継ぎます。 主な役目は寺しばしのときとこのお盆の棚経です。 どちらか一人が上人さんと同行し、お布施を集めます。 各家ではお布施の包み紙に上と書きその下に施主の名前を書いたものを用意しておきます。昔はお 米だったそうです。 初盆の家は少し念仏も長くなります。また、初盆の家ではお供えのおすそ分けの供養の品を2人分 用意し寺年番へ手渡します。 ●初盆の家 この日の夜、初盆の家に親戚、組内の人がお参りします。 住職から回向してもらいます。回向が終わり、いばらもちやお菓子でお茶になります。帰りにお寿 司やサランラップ等など、供養の品をお参りに来てもらった方にわたします。 |
| |
8月14日(灯篭送り) |
|---|
初盆の家では次の行事があります。 11時ごろ親戚、組内の方が夕べのようにお参りに来てもらいます。 このときは上人さんはみえないので、組の代表の方にお勤めの進行役 をやっていただくようお願いします。(灯籠送りの念仏) お盆のときの広出組の人はご仏前など一切用意なしでふじ文のをみ用 意する慣習です。 代表の方の念仏が終わると、皆さんに食事をしていただき時間によっては一旦家に戻ってもらいます。 そのときお供えなど分け、供養の品を各自持って帰ってもらいます。 そうしてお昼過ぎ改めて皆さん初盆の家に集まりお盆の飾り物をお寺に運びます。お寺で飾られたし ょうろうさんの前にお供えをあげます、ビールなどが一般的です。 念仏講のお参りの方の分もお供えを供えます。 回向料、お灯明料とお米1升をいつもの法事と同じように祭壇に上げます。家であげてもらった皆さ んからのふじ文も忘れないように持ってくること。 お寺で灯篭送りのお勤めが始まります。親戚、組内の方が参列していただき、焼香は順次その場で回 されます。 |
|
| |
8月16日(施餓鬼) |
|---|
12時半お寺の鐘が鳴ります。13時から施餓鬼供養が始まります。 年番さん(自治会役員)は事前に各戸を回り施餓鬼で供養する戒名と お布施を集めます。 一般的には、先祖代代と直近の佛さんの戒名をお願いします。 当日は、住職の回向に続き年番さんが戒名を書き上げ祭壇に上げ、一 人一人が焼香をします。 初盆の家から始まり、組の順番に進められます。 終わるとお菓子と、紙でできた旗のようなもの(施餓鬼旗)を頂きます。 その旗のようなものはお墓に飾ります。その紙でできた旗のようなものが、早く溶けてなくなることが供 養につながるとのことである。 写真の施餓鬼旗はいつの日か渡されなくなった。  |
|
| |
8月23日合同灯篭送り |
|---|
| 合同灯篭送り供養の日です。 午後初盆の家の方々がお寺参りします。 灯篭送りの供養がされます。これでもって、しょうろうさんなどがお寺さんによって処分していただ くことになるそうです。 法事と同じように、回向料とお米1升、ふじ文をあげます。 |
| |
| お年寄りから聞いたお盆の話 |
|---|
| 昔のお盆のお話を長老から聞きました。 昔は7日の火入れの時に、軒下に自分で作った提灯をぶら下げたそうです。 その提灯にろうそくを燈し、夕方毎日お墓参りをしたそうです。 火入れから一週間は毎日お墓参りし、灯篭さんにろうそくを上げ、その火が消えてなくなるまでお墓 にいた習慣があったそうです。 |
| |
番外 |
|---|
| 誕生寺は平成27年2月から無住のお寺となりました。 ふる里はすべてが誕生寺の檀家ではなく、半数ほどは他宗の方が混在していますが、このことに伴っ て今までの慣習が変わってきたことがあります。 ・地区のお寺として檀家を問わず誕生寺での法要が営まれましたが、これを境に他宗派の方は行わな い申合せがされました。(従来他宗の方の葬儀は、檀家寺と二重の法要が行われていました) ・時米の志は、檀家の家のみの志となりました。 ・棚経は檀家の家のみとなりました。 ・施餓鬼と永代経、弁天さん(数珠繰り)の自治会主催の法要は従来通り宗派を問わず催されます。 家からの野辺の送りが無くなり、地域とのつながりが疎になってきたことにも起因してきているので はないのかな、とも感じています。 20数年続いた盆踊り大会も、平成28年の自治会総会で廃止と言う申し合わせとなりました。 |
| |