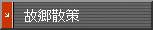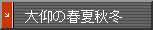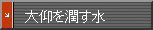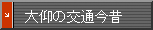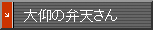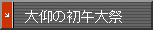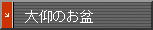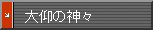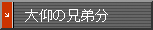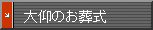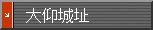・誕生寺の檀徒として記録しておきたい一つで、それは「一丁切り」という行事です。
いつ頃からの出来事か定かではありませんが、自分が子供のころは「寺しばし」という言葉が耳に残っ
ています。
2月に檀家が全員集まり、地区の山などから寺で使う一年分の柴を集めた行事と聞いています。
自分が親の代わりとして地域の行事に参加した頃は「一丁切り」と呼ばれ、境内や本堂の清掃を行いそ
れらが終わり次第ひと回向する内容でした。念仏は特別なものではなく、檀家勤行式によるものです。
 |
 |
話はこれだけなのですが、「一丁切り」とは何なんでしょう。
広辞苑では一丁切りを次のように説明してます。
いっちょうきり【一挺切】(茨城県で)葬式を終わった夜、蝋燭を一本だけともして、それの灯る間
だけ回向すること。
茨城県だけの話?
・大仰の里地内には同じ宗派であるお寺が2家ある。しかし、成福寺も来福寺も「一丁切り」の行事は
ない。隣町の蓮蔵寺で尋ねたところ、「天台真盛宗では、不断念仏の教えはあるが一丁切りは聞いたこ
とがない、誕生寺独自の行事では」とのことであった。
昔は風呂を焚いたり食事の用意に火を使うことから柴は必需品である、それを奉仕作業で準備する風習
は自然な成り行きである。そして、電気やガスが普及し柴が必要なくなった、それじゃ代わりの奉仕作
業を考えようということから「一丁切り」ができたとも推測される。
しかし、「一丁切り」という言葉の発想はどこから来たのだろうか。長い伝統のあるものなのか、それ
ともたまたまのものであるのか真相は分からない。
・真盛上人は嘉吉3年正月28日にお生まれになり、明応4年2月30日に遷化されました。
命日月ということからの供養の一丁切り行事、とも理解はできます。
滋賀県野洲市の広報で見たのであるが、野洲市の小南では百万遍念仏による無病息災を祈念する「一
丁切り」という念仏行事が続いていることを知りました。
誕生寺にも百万遍念仏による「数珠繰り」という行事が年2回あります。
広辞苑では一丁切りを次のように説明してます。
いっちょうきり【一挺切】(茨城県で)葬式を終わった夜、蝋燭を一本だけともして、それの灯る間
だけ回向すること。
茨城県だけの話?
・大仰の里地内には同じ宗派であるお寺が2家ある。しかし、成福寺も来福寺も「一丁切り」の行事は
ない。隣町の蓮蔵寺で尋ねたところ、「天台真盛宗では、不断念仏の教えはあるが一丁切りは聞いたこ
とがない、誕生寺独自の行事では」とのことであった。
昔は風呂を焚いたり食事の用意に火を使うことから柴は必需品である、それを奉仕作業で準備する風習
は自然な成り行きである。そして、電気やガスが普及し柴が必要なくなった、それじゃ代わりの奉仕作
業を考えようということから「一丁切り」ができたとも推測される。
しかし、「一丁切り」という言葉の発想はどこから来たのだろうか。長い伝統のあるものなのか、それ
ともたまたまのものであるのか真相は分からない。
・真盛上人は嘉吉3年正月28日にお生まれになり、明応4年2月30日に遷化されました。
命日月ということからの供養の一丁切り行事、とも理解はできます。
滋賀県野洲市の広報で見たのであるが、野洲市の小南では百万遍念仏による無病息災を祈念する「一
丁切り」という念仏行事が続いていることを知りました。
誕生寺にも百万遍念仏による「数珠繰り」という行事が年2回あります。
 誕生寺数珠繰り
誕生寺数珠繰り |
 |
これも通称は「弁天さん」と呼ばれており何かちぐはぐさが感じられ、この数珠繰りこそ「一丁切り」
と深い関わりがあるのではないかと最近感じています。
「寺しばし」イコール「一丁切り」なのか「寺しばし」と「一丁切り」なのか、「弁天さん」イコール
「数珠繰り」なのか「弁天さん」と「数珠繰り」なのか、どうもあやふやな中で伝承されてきた感じが
します。檀徒としてあまり気にせず来たことに原因もあるが、平成27年に誕生寺は無住となり教えを
乞う人はいない。
ところで
・平成27年にこの「大仰の里」のホームページがご縁で、千葉県にお住いの村田一男先生から一丁切
りに関わる問い合わせをいただきました。長年教鞭を取られ、八千代市郷土博物館館長や八千代市郷土
歴史研究会顧問などを務められている方だと後程知りました。
そして長年「一丁切念仏講」を研究されており、平成29年村田一男先
生喜寿記念論集編集委員会の皆さんにより「村田一男先生喜寿記念論集
地域史の再検討」が刊行され、「壹挺切念佛」考が掲載されました。
誠に恐縮なことですが謹呈として手元に届けて頂きました。
執筆のきっかけは、八千代市下市場にある壹挺切念佛講の供養塔からだ
そうですが、我がふる里周辺には同じような供養塔は見つかりません。
誕生寺も含む全国13か所のお寺さんを調査されていますが、一丁切り
の呼び名のある行事は宗派を問わず散見されたが、民間念仏信仰での蝋
燭一本を灯して念仏を唱える事例はなかったとのことである。
「一丁切り」は仏教用語辞典など専門書を探しても記載されていませんでした。蝋燭の数え方はその形
状によって1本、1個、1丁と異なります。燭台に載せた蝋燭は1丁、2丁です。
「一丁切り」の名の起こりは、蝋燭1本をあげて念仏を唱名する時間単位を指し、蝋燭1本を灯し切る
意味であると本の中で述べられています。
また三重に縁のある本居宣長さんの日記には一丁切りの文言が至る所にあり、先生は松阪にも来られ調
査されているが菩提寺でもある樹敬寺には一丁切りの記録は全くなかったとの事である。
本居宣長日記に興味あり後日図書館で読んでみた、その内容は別項「本居宣長日記を読んで」に書き記
すことにした。
誕生寺の一丁切りの謂われについてこれからも気に留めていきたい。
と深い関わりがあるのではないかと最近感じています。
「寺しばし」イコール「一丁切り」なのか「寺しばし」と「一丁切り」なのか、「弁天さん」イコール
「数珠繰り」なのか「弁天さん」と「数珠繰り」なのか、どうもあやふやな中で伝承されてきた感じが
します。檀徒としてあまり気にせず来たことに原因もあるが、平成27年に誕生寺は無住となり教えを
乞う人はいない。
ところで
・平成27年にこの「大仰の里」のホームページがご縁で、千葉県にお住いの村田一男先生から一丁切
りに関わる問い合わせをいただきました。長年教鞭を取られ、八千代市郷土博物館館長や八千代市郷土
歴史研究会顧問などを務められている方だと後程知りました。
 |
そして長年「一丁切念仏講」を研究されており、平成29年村田一男先
生喜寿記念論集編集委員会の皆さんにより「村田一男先生喜寿記念論集
地域史の再検討」が刊行され、「壹挺切念佛」考が掲載されました。
誠に恐縮なことですが謹呈として手元に届けて頂きました。
執筆のきっかけは、八千代市下市場にある壹挺切念佛講の供養塔からだ
そうですが、我がふる里周辺には同じような供養塔は見つかりません。
誕生寺も含む全国13か所のお寺さんを調査されていますが、一丁切り
の呼び名のある行事は宗派を問わず散見されたが、民間念仏信仰での蝋
燭一本を灯して念仏を唱える事例はなかったとのことである。
「一丁切り」は仏教用語辞典など専門書を探しても記載されていませんでした。蝋燭の数え方はその形
状によって1本、1個、1丁と異なります。燭台に載せた蝋燭は1丁、2丁です。
「一丁切り」の名の起こりは、蝋燭1本をあげて念仏を唱名する時間単位を指し、蝋燭1本を灯し切る
意味であると本の中で述べられています。
また三重に縁のある本居宣長さんの日記には一丁切りの文言が至る所にあり、先生は松阪にも来られ調
査されているが菩提寺でもある樹敬寺には一丁切りの記録は全くなかったとの事である。
本居宣長日記に興味あり後日図書館で読んでみた、その内容は別項「本居宣長日記を読んで」に書き記
すことにした。
誕生寺の一丁切りの謂われについてこれからも気に留めていきたい。