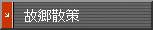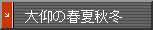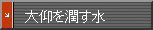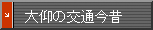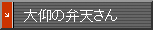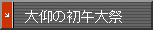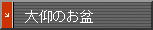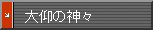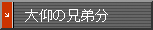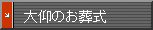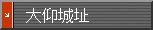平成21年は伊勢湾台風から50年目となるがあの時以来大きな災害はない。
子供のころのしもやけやあかぎれもなく暖冬が続くこの頃、季節感が薄れているものの四季折々の
行事もあり、まったりした時間が過ぎていくわが故郷です。
| 山の神さん |
|---|
| 1月 | |
1月7日は山の神さんです。 山口大池のそばにある山の神さんに朝の5時ごろから自治会の役員さん が集まり、たき火を焚きながらお参りの人を待ちます。 お神酒もふるまわれ、またたき火にあたりながら餅を焼き昔話に花が咲 きます。 帰りにお米を焚き火で炒ってもらい家でご飯と一緒に炊き込み1年の無病息災を祈ります。 令和3年度より、行事の開始を朝の8時からになります。 |
|
| |
| 大井神社弓引き神事(兄弟分) |
|---|
| 1月 | |
上出、村出、片山、向川原の宮年番(兄弟分)が 1月成人の日早朝から 大井神社に集まり弓引きの神事を行います。 神事をした後神殿で兄弟分の杯を交わし親類同様の付き合いを一生続け るとともに助け合っていく習わしが続いています。 弓の的は30mほど先にありなかなか命中しません。 的に命中した本数で五穀豊穣を占います。 兄弟分の維持が困難となり、自治会員から選ばれた氏子総代により執り行うようになりました。 |
|
| |
| どんど焼き |
|---|
1月 |
|
一般に山の神の日に行うところが多いのですが、上出は1月14日お正月 のしめ飾りや去年のすす払いに使った笹などを燃やす行事があります。 年番さんが朝早くから準備します。 焼くところは、公会所から30mほど山側へ行った道の曲がり角で、大 昔から決まっています。 最近は公会所の広場で行うようになりました。 |
|
| |
| 弁天さん |
|---|
| 1月 | |
1月誕生寺の弁天座像の前で「なーむあみだーぶつ」と鉦の音にあわせ て皆で100回念仏を唱えます。 念仏に合わせ数珠をグルグル回し、五穀豊穣、家内安全極楽往生をお祈 りする法要があります。 100回の念仏で100万弁唱えたと同じご利益があると言います。 弁天さんは8月もあります。 皆でまわす数珠は10mほどもある大きなものです。 |
|
| |
| 初寄合・厄祝い |
|---|
1月 |
|
1月弁天さんの終わったあと、15時頃から自治会の初寄合いが公会所 であります。 自治会長さんらから年間の報告などがあり、それらが終わり次第恒例の 厄祝いが開催されます。 男の本厄と還暦の皆さんを祝います。 |
|
| |
| 二の午さん |
|---|
2月 |
|
2月20日は「二の午」さんです。(年により変わる) 昼ごろ自治会の年番さんらが総出で、炭焼きの裏山頂上の小さな石のお 宮さんに参ります。 お参りしてもらった方々にお菓子を配ります。 年の暮れには年番による清掃があります。 大正生まれの母の話では、昔は小豆ご飯で作ったおにぎりを出してもらえたので子供たちが大勢お参りに 行ったものだ、とのことでした。 |
|
| |
| 寺しばし(一丁切り) |
|---|
2月 |
|
2月は誕生寺の檀家衆が集まり「一丁切り」の出合です。 横山住職の頃までは、地区の山から一年分の薪を集めました。 境内の清掃が終わると、真盛上人が亡くなられたのがこの2月であるた め、供養の回向が住職により執り行われます。(この回向が一丁切り) そして、寺世話方の1年の始まりであり、行事予定、会計報告などが催 され続いて会食となり世間話に花が咲いてお開きとなります。(近年は寺年番が取り仕切る会食は無くな りました) 広辞苑によると一挺切りとは「葬式の終わった夜、ロウソクを一本だけともし、それのともっている間だ け回向すること」と説明されている。 ローソクの数え方はその形状により、1本、1個、1丁となります。 燭台で手に持つものは1丁と数えられます。「一丁切り」の語源がここら辺にあるのではと推測されま す。 宗派を問わず、亡くなられた方への供養の法要と無病息災を祈願する行事の2種類が全国的に見られます がその実態は少ない。 誕生寺で「一丁切り」という言葉が残り、継続して回向が行われていることは珍しい事である。 この地域では同業の成福寺、来福寺では行われておらず、蓮蔵寺の住職によると「天台真盛派では不断念 仏の教えはあるが一丁切りは知らない、誕生寺独自の行事では」と話を頂いた。 回向は普通の法事と同じ内容であるが、あえて「一丁切り」と呼称したのかは不詳である。 |
|
| |
| 排水路清掃出合い |
|---|
3月 |
|
3月は自治会役員交代の月であり、排水路の清掃作業があります。 そしてこの席で自治会の新役員が紹介されます。 その後広出組、中組、西組、東組に分かれての排水路の清掃ですが、溜 まった泥の排出はなかなかの重労働です。 とは言え、新年度への恒例の出合い作業です。 |
|
| |
| 用水ポンプアップ |
|---|
4月 |
|||||
4月25日頃田んぼに水があがります。 今日から田に水が引かれます。 ポンプは西と東にあり、山口池の水が足らなくなった場合補給するため のポンプであり、受益者である山口池の係りが持ち回りで管理すること になっています。 近年は山口池の水が使えなくなってきており、池の水の恩恵にあった9町ほどの田圃はこれらのポンプが 頼みの綱になっております。 |
|||||
|
| 山口大池草刈り |
|---|
6月 |
|
上出には山口池という大きな溜め池があり、いつ頃からか上出9町の田を 潤してきました。 農地保全管理の一環として堤の草刈り出合い作業が年2回あります。 平成26年から山口池は土地改良区の管理となりました。 受益者が減ったため、28年度から地権者全員で年2回の草刈りを行うことになりました。 |
|
| |
| 鮎漁解禁 |
|---|
6月 |
|
川上さんを源にする雲出川は水豊な川です。 昭和30年代本当にきれいな川でした。でも台風時期は恐かった! 堤防も整備され台風の怖さはなくなりましたが、ぎぎ、砂ほりやもろこ やたびら等見られません。 6月になると大井小学校前は賑わいます、そうです、鮎の解禁日です。 片山橋付近の瀬は鮎の友釣り場です。子供の頃の瀬はもっともっときれいだった。 釣り人も沢山いた・・・・・。 |
|
| |
| 祇園さん |
|---|
7月 |
|
7月14日は祇園さんです。 公会所の横に祇園さんがあります。 13時年番が集まり、祇園さんを開けるとともに軒下にちょうちんの準 備をします。 お参りに来て頂いたかたがたにお菓子を配ります。 疫病を鎮める神様を祭る行事が、故里にも伝わっています。 近年は14日に近い日曜日に開催されます。 祇園さんの境内には、天明4年と刻まれた灯篭があります。 |
|
| |
| 盆踊り |
|---|
8月 |
|
平成20年で20回目を迎える上出の盆踊りが、公会所の広場で開催さ れます。早朝から出合いにより櫓が組みたてられます。 主役は子供、子供たちも昔に比べ少なくなってしまいましたが、夏休み に入ると太鼓の練習に余念がりません。 夕刻5時ごろから会食があり、カラオケの部、花火大会と盛りだくさん の1日です。最後は大抽選会でお開きです。 広場ではかき氷や懐かしいラムネ屋さんが出ます。 しかし、平成28年の自治会総会で、盆踊り大会の廃止が申し合わされました。 |
|
| |
| 施餓鬼 |
|---|
8月 |
|
お盆の行事です。 お盆は8月7日の火入れ(初盆の家で飾り付け)で始まり13日の棚業 (住職が檀家を回り回向)、夜初盆の家のお参りとなります。 翌日初盆の家へ灯籠送りのお参りをし16日が施餓鬼です。 施餓鬼とは、供養に恵まれないもろもろの霊に対しての供養を施す意味 です。 年番は7日ごろ各戸を回り施餓鬼志と戒名をあつめます。当日は寺年番が戒名を書き写し、一軒毎に回向 に合わせ祭壇へ運びます。 |
|
| |
| 地区運動会 |
|---|
9月 |
|
地区運動会が大井小学校の運動場で開催されます。 高齢化、子供さんがいないことなどで出場してもらう選手を集めるのが 大変困難な時代になってきました。 競技種目に工夫を凝らし、お年寄りにも楽しめるものになっていくと思 います。 |
|
| |
| 防災演習 |
|---|
9月 |
|
災害は忘れた頃にやってくる。 恒例の防災訓練が公会所で実施されます。 伊勢湾台風などの災害はまだまだ記憶に新しいところですが、大仰地区 は火災など大きな事件の少ないところです。 消防団員の説明に耳をかたむけ真剣に消火訓練を受けます。 |
|
| |
| 秋の収穫 |
|---|
9月 |
||||||
一斉に稲刈りが始まります。 最近はほとんど9月の初めには実りの収穫となります。 減反減反とはいえ黄金色に色づく季節は活気ある楽しい時期です。 |
||||||
|
12月 |
|
一年の締めくくりは誕生寺での除夜の鐘です。 紅白歌合戦が終わる頃、何処からともなくふる里に鐘の音が響きます。 あちこちのお寺からの除夜の鐘です。 ふる里の誕生寺は、昔から檀家やお参りの人たちにより108つの鐘を 撞いてもらっております。 |