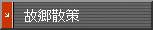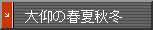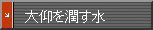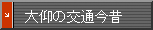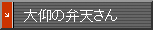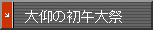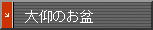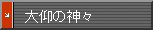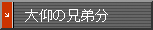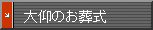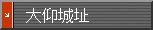仏教大学史学科の大原秦さんと、この「大仰の里」ホームページがご縁で知り合いになりました。
そして大仰に古くから伝わる「兄弟分」の行事の探索に関わることになりました。
| 大原秦の論文「兄弟分はなぜ取り入れられたか」 |
|---|
兄弟分と弓引き神事 大仰の里には古くから蛇山の伝説があり、大井神社では この伝説にちなんで悪霊の退散、村内の平安、五穀豊穣を 祈願する兄弟分による弓引き神事が行われてきました。 歴史的に見ると17世紀の前半、井生、井関、田尻、波 瀬の各村は、津藩から紀州藩に属するようになりました。 また17世紀後半には、片野、小山、八太、其村、庄村、 日置、高野、其倉、石橋の各村は、津藩から久居藩に属するようになり大仰村だけが津藩に残りま した。これ以降明治4年(1871)まで、大仰は他藩の村に囲まれる形となってしまいました。 そこで、大仰村の4地区からなる兄弟分と組み合わせ、大仰内の団結を強める目的でいつしか弓引き の神事として神社に伝わったといわれています。 出典:郷土史ガイドNo35(平成7年2月号) 兄弟分は諸説いろいろあるようですが、縦社会にまつわる話しが多いなか、横社会のつながりに着 目した大原さんの目にはどう映ったのでしょう。宮崎四郎様、田中久吉様から貴重なお話を伺いまと められた大原さんの論文から大仰の兄弟分を解説します。 「大仰の兄弟分慣行と宮座」 大原秦著 へのリンク
兄弟分:大仰村は、村出、上出、片山、向川原の4地区からなっており、4地区ごとの血縁でもない家 の跡取り息子が兄弟分の盃を交わし、親戚同様の付き合いをする風習がありました。 |
|
| |
| 波及的効果「菅笠日記」 |
|---|
大原さんとの出会いから、本居宣長「菅笠日記」を知ることができました。 明和9年本居宣長43歳の春、5人で吉野に旅をし、大仰を通っているのです。 「本居宣長記念館のホームページ」で楽しく解説されています。必見!! 一志郷土史では、一志郷土文化研究会郷土文化一志第5集(昭和58年3月発行)「初瀬街道の今 昔」吉村篤著にも興味ある内容がありました。 |
| 【補遺】 少子高齢化、他地域への転出などにより「兄弟分」の選定が無理となってきた。 これらの経緯を踏まえ、平成29年12月に今後の対応が提案された。 その結果、兄弟分の慣習は廃止され各自治会から3名の氏子総代を選出し、弓引き神事は氏子 総代の中から人選し執り行うことに申し合された。 |